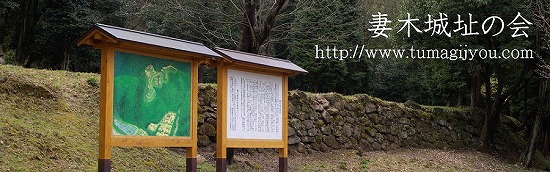ようこそ妻木城址の会オフィシャルサイトへ
岐阜県土岐市妻木町は、岐阜県の東南部に位置し妻木城跡や崇禅寺、八幡神社など多数の史跡や文化財を今に残している町です。

平成7年に発足した「妻木城址の会」は、私たちが子どもの頃から慣れ親しんできた豊かな自然と歴史遺産を未来まで守り伝える事を目的として活動しています。
また 地域の歴史を掘り起こし、伝統行事を守り伝えることによって、いつまでも地域住民が自慢できる町でありたいと考えています。

妻木城は標高409mの城山の山頂に築かれた山城です。また、城山の北側山麓には、御殿跡、士屋敷跡の遺構が残されています。
いつ築城されたかは定かではありませんが、一説には暦応2年(1339年)に土岐明智彦九郎頼重が祖父である美濃国守護職土岐伯耆入道頼貞の遺領を継ぎ、妻木郷の領主になった後に築城されたと言われます。
しかし、近年の発掘調査によって戦国時代に築城されたことが明らかになってきました。この地方は戦国時代、武田氏と織田信長の両勢力の接点に辺り、織田方の城として防備が整えられていったものと考えられます。

妻木氏は関ヶ原の戦い(1600年)に徳川家康に味方し、その戦功により土岐群内7500石の交代寄合(参勤交代をする旗本)として妻木陣屋を拡張整備しました。しかし、万治元年(1658年)領主の急死により跡継ぎが無く、妻木氏は断絶となり妻木陣屋(妻木城)は取り壊されました。

妻木城は時代とともに改修されてきました。山上には本丸、二の丸、三の丸、太鼓櫓、蔵跡などの伝承があり、また、山麓には関ヶ原の戦い以後大改修されたと思われる妻木陣屋(御殿跡・士屋敷)の区画が石垣とともに残されています。貴重な遺構として岐阜県史跡に指定されています。